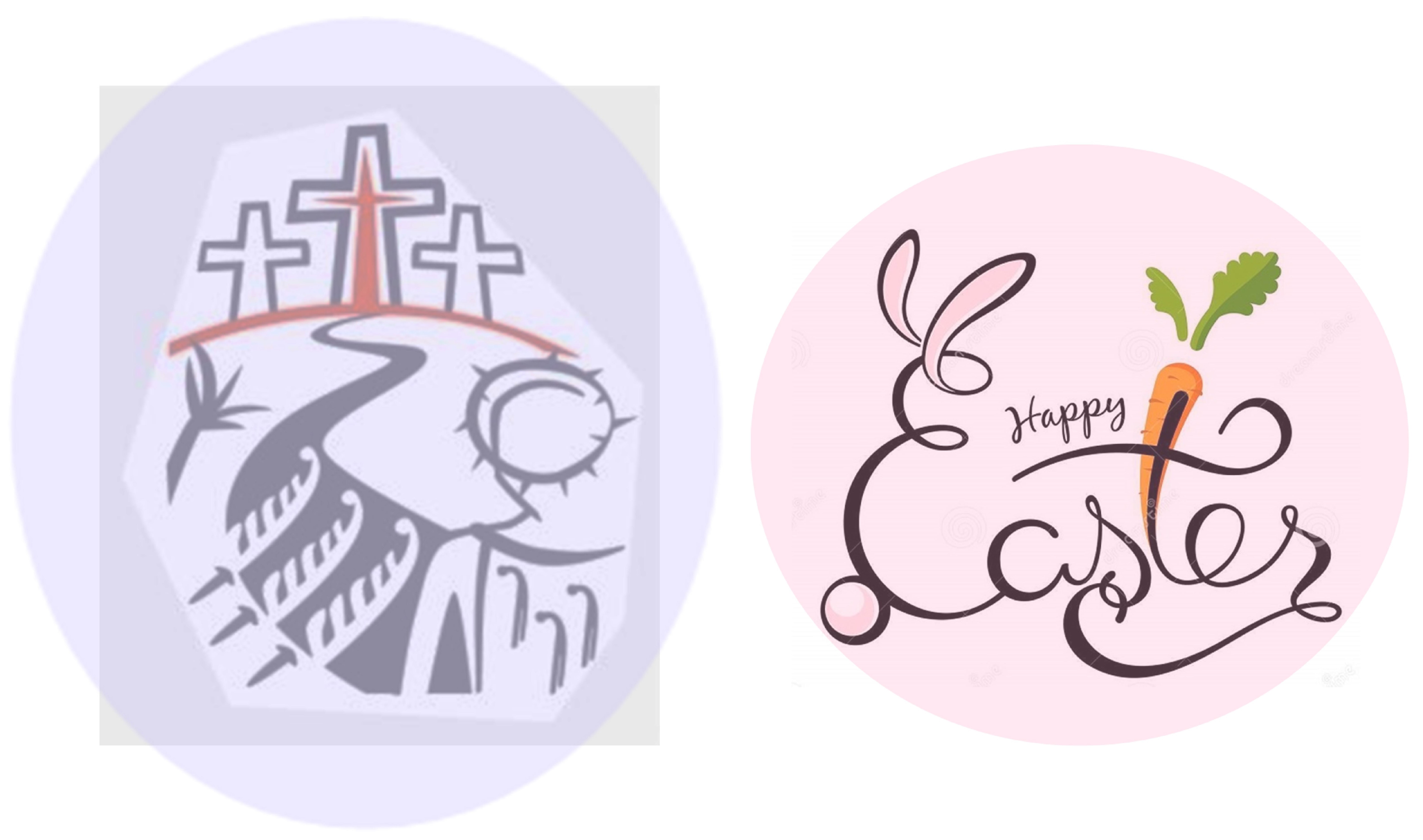『 主のうちに闇はなく 』
2017年12月3日(日)
Ⅰテサロニケ5:1-11
11/23、共愛学園で行なわれた地区大会では、講師の片岡夫妻から福島原発事故とその後の福島の状況についてお話をうかがった。今日の聖書に「人々が無事だ、安全だと言っているその矢先に突然破滅が襲う」と記されていたが、その言葉が現実のものとなったように事故が起こり、その後の状況の中で多くの人が今も苦しみ悩んでいる。しかし一方では、それらのことが「なかったかのように」再稼働が進められようとしている。
今年もアドベントを迎えた。私たちを絶望へと追いやる暗闇の中に、救いの光をもたらす方として救い主がお生まれになった…そのことを喜び祝う季節である。しかしその希望の光は、闇の部分をしっかり見つめようとするからこそ輝いて見えるものなのではないだろうか。絶望の闇が広がっているのに、それに気付きもしないで、気付いても見て見ぬふりをして、「無事だ、安全だ」と楽観する限りにおいては、私たちは本当の救いというものをも見過ごしてしまうのではないかと思うのだ。
私たちの眼差しはすぐに目先のこと、華やかで便利で楽しげなものに惑わされる。キラキラ輝くクリスマスのイルミネーションを見ると心を躍らせられる。しかしイエス・キリストによって与えられたまことの光は、そのような装飾品のような光ではなく、闇の中をくぐり抜けた光、闇の中にまたたく光なのではないか。
「私たちは光の子であって、夜にも闇にも属していない」とパウロは記す(5:5)。テサロニケの手紙はパウロの伝道活動の初期、即ち彼が終末の到来を切迫感をもって語ってきた時期のものとされている。4章には「(主が来られる日=終末には)私たち生き残っている者が空中で主と出会うために、雲に包まれて引き上げられます」という記述がある。「終わりの日が来ても大丈夫。我々は光の子なのだから、滅びずに救われる」そう言いたいのだろうか。
「世界が滅んでも我々は救われる」という信仰は、大きな危うさを内包していると思う。それはいつしか「私が救われるなら、世界が滅んでも構わない」という意識になりかねないからだ。
「神はひとり子を与えるほどに、この世を愛された。」(ヨハネ3:16) 「クリスチャンだけ」を愛された、のではない。「この世」を愛し救うために、神はひとり子を「世の光」として遣われたのだ。「光の子とされる」とは、その光に従い、「ひとりも滅びぬように」との神の御心をこの世に果たし得る歩みを求める人のことだと思う。
私たちの心にも、またこの世の現実にも、様々な闇の現実がある。しかし主のうちには闇がなく、私たちを導いて下さる。そのことを信じるならば、そこに希望がある。