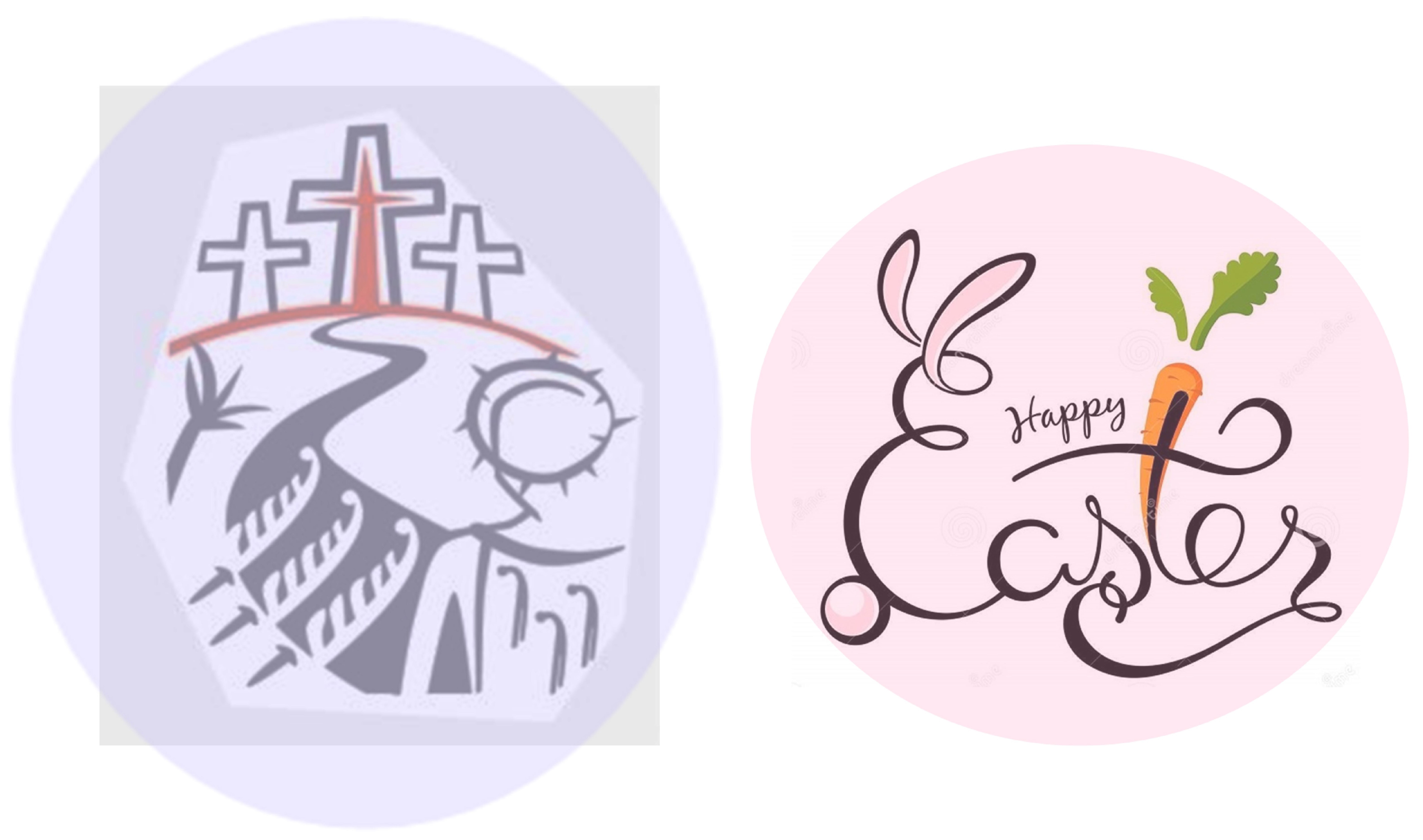『 しょせん「肉の人」同士 』
2020年8月23日(日)
Ⅰコリント3:4-9
キリスト教は「人はみな罪人」という人間理解に立つ。性悪説である。牧師の息子として生まれた子ども時代、すぐに人を罪人扱いする決めつけがイヤでたまらなかった。しかし、では「お前は罪人ではないのか」と言われると、まったく違う。自分の中に醜い思いが満ち満ちているのを認めざるを得ない。そんな自分の姿を知っておくことが大切だと次第に気付くようになった。
パウロはコリントの人々のことを「肉の人」と呼んでいる。「霊の人」に対置する呼称で、いくらかの非難が込められている。それはコリント教会に、教会の内部対立という大きな問題があったからだ。
コリントの教会はパウロによって作られた教会だが、パウロはずっと駐在していたわけではない。地球海沿岸を宣教して歩いたパウロ、その不在の間は別の指導者(アポロ、ケファ=ペトロ等々)が交代で指導していた。その指導者への信頼度や好感度によって、教会内に分派ができ互いに争うようになっていた。その問題を解決するために書かれたのが「コリントの信徒への手紙」である。
人間的な感情によって互いに争っている教会の人々のことを、パウロは「肉の人・ただの人」と呼んでいる。パウロは「お前たちはそんな『ただの人』でいちゃダメだ。もっと正しく立派な『霊の人』にならなければいけないのだ!」そのように言いたいのだろうか?
実はパウロ自身が自分のことを「肉の人」と呼んでいる箇所がある。ローマ書の7章、パウロの「罪の告白」の部分である。「自分が望むことは実行せず、憎んでいる悪を行なってしまう…」そんな自分のことを「肉の人」(ローマ7:14)と称しているのだ。
パウロがコリントの人々を「肉の人」と呼ぶのは、ただの非難の言葉ではない。「偉そうに手紙を書いてる私だってそうなんだ、人間はしょせんみな同じ罪人なんだ」という思いがあったのではないかと思う。「コリントの教会に信仰の苗を植えた私(パウロ)も、植えられた苗に水を注いだアポロも、たまたま指導者の立場にはいるけど、あなた方と同じ『肉の人』なのだ、成長させて下さるのは神なのだ、だからそんな『肉の人』のことで分裂し派閥争いをする愚かさに気付こうじゃないか」…今日の箇所にはそんな思いが込められていると思う。
私たちは「自分が正しい」と思い込むと、異なる考えの人を批判し、否定し、憎むようになる。しかし「自分なんてそんな大した人間じゃないんだ」と思っている心の中からは、攻撃的な思いも少なくなるのではないか。「強さ」を誇示し合って対立してしまう相手との間でも、お互いの「弱さ」を知るときに、共感の余地が生まれるのではないだろうか。
禅宗には「人間所詮糞袋」という教えがあるという。忌野清志郎は「自分が人間のクズだと思えば、素晴しい世界が来る」と言った。「しょせん『肉の人』同士」…そのように思えるとき、そこに平和・共存への扉が開かれる。
その「肉の人」に過ぎない存在を、それでも神は愛して下さる。しょせん『肉の人』である私たちを、それでもイエスは見捨てず、導いて下さる。その愛と導きを信じるとき、私たちは聖霊の力によって「霊の人」へと成長させられてゆくのだ。