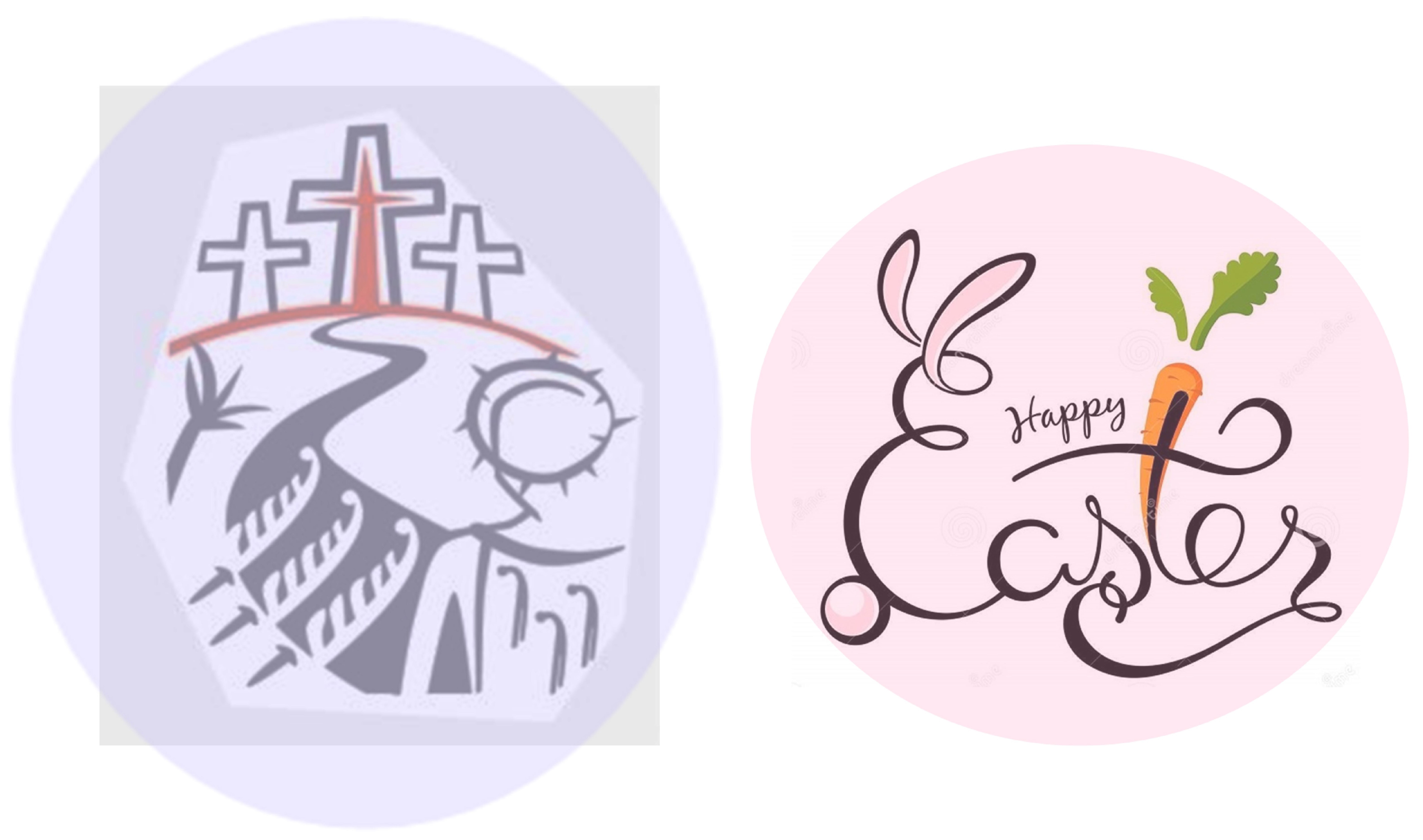『いのちあるときも、死のかなたにおいても』
2023年11月5日(日) 召天者記念礼拝
創世記3:15-20、ヨハネ3:13-18
人間は、自分が死ぬことを知っている、自然界唯一の動物である。だから身近な人が亡くなると悲しみを抱き、葬儀をし、墓に納める。「終わりを知っている」ということが、「今という時のかけがえのなさ」に思いを至らせる。
そのような人間の心の中に、さらなる問いが生まれる。なぜ我々は死ぬのか、死んだらどこに行くのか、と。死後のことを考えると不安や恐れを抱く。そんな問いや不安・恐れの中から、宗教という営みが生まれた。
人はなぜ死ぬのか ― この問いに一つの答えを示すのが今日の旧約の箇所だ。アダムとエバの「原罪」。神さまから「食べてはならぬ」と言われていた木の実を食べ、神に等しい者になろうとした「罪」ゆえに、人は楽園を追放され、そして死すべきさだめとなった…そう記される。「人が死ぬのは罪を犯したことへの罰」ということだ。ここだけを見れば、とても厳しい聖書の教えである。
しかし聖書にはそのような冷徹な裁きのみが語られているのではない。死への不安や恐れを抱く人間に対して、一つの慰めを与える信仰を指し示してくれる。
「神は、独り子をお与えになったほどに世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。」今日の新約、ヨハネ3:16は、聖書の究極の福音を示す言葉として、しばしば引用される。神さまは罪に満ちた世に住む人間を救うために、ひとり子イエス・キリストを世に遣わし、永遠の命に入る道を示して下さった、そこに神の愛がある…そんなことを示す言葉である。
「永遠の命を与える」それが神の救い・神の愛だとヨハネは語る。ではその永遠の命とは何だろうか。未来永劫、いつまでも死ぬことなく今のまま生き続けることだろうか。イエス・キリストを信じたらその見返りとして「いつまでも死なない命」が与えられるということなのだろうか。
正直に申し上げると、私は永遠の命というものが「いつまでも死なない命」だとは思えない。これは私が3歳の時に母と死に別れ、以後「お母さんとは会えないんだ」という心を持って人生を歩んできたことと関係があるように思う。「永遠の命について、もっと違う、別な考え方があるのではないか…」そんな思いを抱えながら、牧師となり、聖書に記された永遠の命のメッセージと向き合ってきた。
永遠の命について、私は次のような考え方へと導かれている。私たち自身が永遠に生きるわけではない。私たちはあくまで、限りある命を生きるものである。しかしそんな私たちが、「永遠なるもの」に触れる時がある、感じる時がある。その一瞬を「永遠の命」と呼ぶのではないか…と。
「肉なる者は草に等しい。草は枯れ、花はしぼむ。しかし神の言葉がとこしえに立つ」(イザヤ40章)。やがて枯れる草に等しい人間が、永遠なる神に包まれる時、そこに永遠の命がある…ということ。十字架の死をもってしても、イエス・キリストの福音(教え・生きざま)は死ななかった、終わらなかった。そんな、いつまでも変わらない福音に出会い、導かれて、「生まれてきてよかった」と思える…、永遠の命とは、そんな経験のことではないかと思うのだ。
「いのちある時も、死の時も、死のかなたにおいても神は私たちと共にある。私たちはひとりではない。」(カナダ合同教会信仰告白より)。そのような信仰に立てる時、私たちはきっと永遠の命に包まれている。